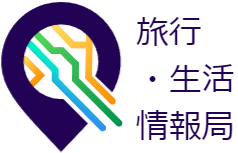宇都宮線(正式名称:東北本線のうち東京近郊区間の上野駅〜宇都宮駅間)は、首都圏と栃木県を結ぶ重要な路線として多くの乗客が利用しています。
しかし、この路線には在来線の「特急列車」が運行されていません。
特急列車は通常、遠距離の移動や観光需要、ビジネス需要に応えるために設定されることが多いのですが、なぜ宇都宮線には特急が存在しないのでしょうか。
本記事では、その理由や背景、そして近年の乗客需要動向などを交えながら詳しく解説します。
宇都宮線の概要

宇都宮線は、一般的には東京(上野駅・東京駅)から大宮駅・宇都宮駅などを経由し、栃木県の黒磯駅までを指す在来線区間を指します。正式には東京駅と盛岡駅の間を結ぶ東北本線の一部ですが、通勤・通学需要の多さや沿線都市へのアクセスの便利さから、沿線自治体の要望によりJR化後すぐから「宇都宮線」の愛称が付与され、以降は宇都宮線と主に呼ばれています。
- 主な区間: 東京駅・上野駅〜大宮駅〜宇都宮駅、宇都宮駅~黒磯駅
かつては東京方面から黒磯駅まで直通する列車もありましたが、現在は小山からの直通のみとなっております。 - 運行形態: 普通列車、快速「ラビット」、湘南新宿ライン、上野東京ラインなど
- 所要時間: 東京駅〜宇都宮駅間は、普通列車で約1時間50分〜2時間前後
この区間は、埼玉県北部から栃木県南部へ向かう通勤利用者や県外からのビジネス利用者が多いことで知られています。朝や夕方のラッシュ時には、かなりの混雑が発生する路線です。
宇都宮線の沿革とかつての優等列車事情

宇都宮線(東北本線)の歴史を振り返ると、かつては東北方面へ向かう特急や急行などの優等列車が通過していました。

あの頃、急行「八甲田」に乗るために、上野駅の低いホームで、まだドアが開く前から上野駅の放送を聞きながら並んでいた。
座席での移動だったのに、どこか旅館のような安心感があって、あの日は不思議と楽しかった。
飛行機ではなく、寝台特急という“動くホテル”で夜を越えた時代。
「カシオペア」「北斗星」「夢空間」「エルム」……北海道から昼間の東京へと帰ってくる、その姿を眺めるのが好きだった。
宇都宮線は、そんな“特急街道”の一部として、生きていた。
しかし、東北新幹線の開業や特急・急行の系統再編に伴い、在来線特急は大幅に縮小されてきました。
- 急行列車の衰退
かつて東北本線では夜行の「八甲田」をはじめとした急行列車が多数走っていましたが、新幹線の開業や特急の増発によって役割が変わり、多くの急行が廃止されています。 - 特急列車の再編
「特急はつかり」「特急やまびこ」など、東北新幹線開業以前は在来線経由で東北方面へ向かう優等列車が運行されていました。しかし新幹線が整備されるにつれ、長距離客は新幹線へ移行。結果的に在来線特急の需要は激減していきました。 - 日光方面への特急設定
実は宇都宮線区間の途中から分岐して日光方面へ向かう特急列車(「日光」「きぬがわ」「スペーシア日光」「スペーシアきぬがわ」など)が存在します。ただし、こちらは東武との共同運行であり、宇都宮駅や那須塩原駅を発着とする純粋な「宇都宮線の特急」とは趣旨が異なります。かつては、国鉄・JR(宇都宮線・日光線経由)と東武鉄道でそれぞれ対抗して日光方面に特急列車を走らせていましたが、現在は競争する形はなくなっています。
そうして特急列車が減っていったことで、駅の風景も静かに変わっていきました。
たとえば宇都宮駅――かつてはホームに駅弁を手にした立ち売りの人がいて、特急だけでなく、普通列車が到着しても変わらず弁当を差し出していた。
2000年代に入ってからも、まだその風景は残っていて、いつものように駅に立つ姿を見かけた人も多かったはずです。
けれど今、その光景はすっかり姿を消してしまいました。
新幹線が開業してしまい、「旅の余白が消えて」なくなっていった風景もかつてはありました。
特急列車が運行されない4つの理由
ここでは、実際に「なぜ宇都宮線に特急列車が設定されないのか」を4つの観点から詳しく解説します。
東北新幹線との競合

最も大きな理由は、東北新幹線との競合です。東京〜宇都宮間は東北新幹線を利用すれば、最速で約50分程度で到着します。
- 新幹線という高速輸送手段がある
- ビジネス客は特急よりもさらに速い新幹線を選ぶ
- 在来線特急を新たに走らせても時間短縮効果は限定的
在来線の特急列車を設定するとしても、新幹線と比較して乗車時間に大きなアドバンテージを得ることは難しく、多くのビジネス利用客は圧倒的に速い新幹線を選びます。よって、特急料金を払ってまで在来線特急に乗ろうとする人が少なくなると考えられます。
かつてはJR特急は自由席特急券が発売されていましたが、近年全席指定席の特急列車が多く運転されており、新幹線との差額が少ないため、利用価値はなおさら低くなっているでしょう。
一方で宇都宮から黒磯方面の各駅は新幹線が止まらないことが多いため、乗り換えなしで移動するという意味では、特急列車は楽に移動できた交通手段かもしれません。
通勤路線としての性格

宇都宮線は特に大宮〜小山〜宇都宮といった区間において、通勤・通学路線としての色合いが非常に強いことも理由の一つです。日々のラッシュ時には15両編成の電車が頻繁に運行され、多数の利用者の足となっています。
- ラッシュ時を中心に輸送力が求められる
- 定期利用者が多く、特急よりも普通列車が重視される
- 通勤利用者にとっては座席指定や特急料金より、運賃のみで利用できる列車本数・発着頻度が大事
特急列車の導入には専用車両の投入やダイヤの確保などが必要となり、通勤時間帯の過密ダイヤとの両立は難しい側面があります。限られた線路容量を、より多くの普通列車・快速列車に振り分けることが利用者全体にとっての利便性向上につながっているのです。
かつては特急列車の運転のために、待避線が用意されている駅もありましたが、エレベーター設置のためにつぶされてしまっている駅もあり、現在は難しいでしょう。また、利用客の多い通勤時間帯はダイヤが過密で通常より時間がかかり退避駅もないため、特急列車よりも普通列車グリーン車で十分という可能性が高いです。
快速・普通列車の利便性向上
近年は「上野東京ライン」や「湘南新宿ライン」の開業・拡充に伴い、宇都宮線の利便性が大幅に上がりました。東京駅まで乗り換えなしで行けるだけでなく、横浜方面や新宿方面へも直通する列車が増えています。
- 上野東京ラインにより、東海道線や高崎線と一体的なダイヤ運行
- 湘南新宿ラインによる新宿・渋谷方面へのアクセス向上
- 一部の快速「ラビット」など、普通列車より速達性の高い列車も運行
このように、歴史的にも特急なすのを快速に格下げして速達性を上げた経緯があり、在来線の中で「特急」に近い感覚で利用できる快速列車の拡充が行われており、従来の「急行・特急」的役割をある程度カバーできているといえます。追加料金が不要で、かつ主要駅を中心に停車する快速列車があれば、特急を運行するメリットがますます薄れてしまうのです。
ただし、近年のダイヤ改正で夕方ラッシュ以降の上野発着の快速列車がサイレントで減便されたり、ダイヤの速達性がサイレントで遅くなっていたりと、ダイヤの改悪が行われているのも現状で、これには宇都宮線利用客からも不満が出ています。
宇都宮線における観光需要とその対応策

宇都宮線沿線には宇都宮市をはじめ、佐野市、小山市、そして日光観光の玄関口となる宇都宮駅など観光の拠点が点在しています。特に宇都宮は「餃子の街」として全国的に有名であり、多くの観光客が訪れます。しかし、この観光需要も「在来線特急」を走らせるほどの集客力があるかというと、以下の点を考慮する必要があります。
- 日光方面は別ルートや他社線が強い
東武線の特急「スペーシア(けごん・きぬ)」「リバティ(リバティけごん・リバティきぬ・リバティ会津)」「スペーシアX」などが観光客のアクセスとして人気があります。JR日光線経由の「特急日光」も設定がありますが、これはあくまでも新宿方面から日光へ直通する列車であり、宇都宮線の沿線需要をターゲットとした特急ではありません。 - 宇都宮市自体はアクセスしやすい
東京駅から普通列車でも2時間弱、新幹線なら約50分でアクセス可能です。「わざわざ特急を利用して行く距離」よりも、「ちょっとした日帰り旅行や仕事ついでに行ける街」として認識されている面が強く、特急としての需要はあまり高くありません。 - 宇都宮市内での観光移動はバスやレンタカーが主流
餃子店巡りや大谷資料館、宇都宮城址公園などの観光地が点在しているものの、市内移動はバスやタクシー、レンタカーがメインとなるため、特急を使う場面はそもそも少ないという現状があります。 - 近年宇都宮LRT(路面電車)による新たな移動手段も追加
これらを総合すると、観光需要だけで在来線特急を走らせる意義が十分でないと判断されていると言えるでしょう。
今後の展望:新たな列車設定の可能性は?
現状、宇都宮線に特急を設定する具体的な計画は公表されていません。しかし、近年の鉄道界では、通勤特急や「座席指定サービス」を導入する動きが各社でみられます。
- 通勤特急・ホームライナーの設定
首都圏のJRでは、東海道線の「ホームライナー」や中央線の「中央ライナー」など、追加料金を払えば座って帰宅できるサービスを導入している例があります。宇都宮線でも一時期「ホームタウンとちぎ」「ホームライナー古河」などの列車が運行されていましたが、ダイヤ改正で廃止されました。混雑緩和や快適需要に応えるための着席サービスは今後再注目されるかもしれません。 - グリーン車の拡充
JR東日本は宇都宮線を含む首都圏の主要路線にグリーン車を連結しており、追加料金を支払えば確実に座席を確保できる仕組みになっています。現状ではこれが「特急並みの快適さを在来線で得る方法」として機能しており、特急が設定されない代替として利用されています。 - 新型車両・サービスの導入
快速「ラビット」や特別快速を設定するなどのダイヤ改正で、実質的な速達列車を強化する可能性もあります。しかし、既存の通勤需要優先のダイヤを大幅に変更するのは容易ではなく、また「特急」に統合してしまうと利用客が減りかねないため、慎重に検討されると考えられます。
以上の点から、近い将来に宇都宮線に「特急列車」が復活する可能性は低いと考えられますが、都心への直通や座席指定サービスなどの利便性向上施策は引き続き注目されるでしょう。
一時的なら特急列車並みの列車が運転された経緯も
ごく稀ですが、東北新幹線が不通になったケースで東北新幹線の代替輸送列車としていわゆる「救済臨」が運転されたことがあります。運転区間は上野から那須塩原間、那須塩原~仙台間で運転されました。
上野から那須塩原間は185系で運転されたときは爆速で運転されていて、特急列車並みの速度で運転されたことがあり、途中駅は那須塩原、宇都宮、小山、大宮、上野と停車するダイヤで料金不要の臨時快速列車として運転されましたが、この列車は特急列車さながらで、定期列車を待避線に入れて追い越すなど往年の東北本線特急を感じさせる列車でした。
しかし、E257系で運転された際には鉄道ファンがグリーン車に殺到した時もあったほか、185系で大宮から上野まで立ち席が出るほど鉄道ファンが乗ってきたことから、ダイヤが次第に遅くなってきています。
那須塩原~仙台間でも臨時快速列車が運転され、特急いなほに使用されているE653系を那須塩原まで回送させた際に宇都宮線も走行しました。こちらも特急列車さながらの臨時快速列車で、受験生や多くの輸送客を運びました。
そういえばなんで宇都宮線の特急って走ってたの?
宇都宮線が「特急街道」だった理由は、単に東北への通過ルートだったから――ではありません。
もう少し、地図と歴史をさかのぼってみると、この路線が選ばれた背景が見えてきます。

もともと江戸時代、日光街道は“参詣と将軍家”にまつわる重要な道で、
宿場町として栄えたのは、栗橋、幸手、草加、千住など、現在の東武日光線に沿ったルートでした。
ところが鉄道が整備され始めた明治時代、高崎方面へ向かう幹線が先に建設され、
その後、東北方面へ伸ばすにあたり「どこで分岐するか」が問われました。
結果として選ばれたのが、直線ルートを取りやすく、橋梁が少なくて済む「大宮駅」だったのです。
当時、大宮は門前町であり宿場町でもありましたが、最初は鉄道の停車駅ですらありませんでした。
けれど、分岐駅に選ばれたことをきっかけに、鉄道の要所として再生を遂げます。
操車場、工場、車両基地――鉄道の裏方を担う設備が集中し、それを支える人々が集まり、
今の大宮の発展へとつながっていくのです。
つまり、宇都宮線に特急が走っていたのは、単に“東北に向かう途中だったから”ではなく、
地理と構造と暮らしが選び取った、合理的でありながら歴史の余韻を残すルートだったとも言えます。
当時の停車駅を見ると確かに宿場町を意識した停車駅に
かつて宇都宮線を走っていた特急列車や急行列車は、いまの感覚とは少し違う停車パターンで運行されていました。
停車駅は、大宮、蓮田、久喜、古河、小山、石橋、宇都宮、宝積寺、氏家、矢板、西那須野、そして黒磯。

現在は東北新幹線の主要駅となっている那須塩原駅も、当時は通過駅でした。
そして、もう一つ時代を感じさせるのが、湘南新宿ラインがまだ存在していなかったということ。
いまは直通で行ける新宿や池袋、赤羽といった都心方面へも、当時は上野駅からの乗り換えが基本でした。
また、現在の主要駅である浦和駅やさいたま新都心駅も、かつては停車駅として整備されておらず、
浦和駅は貨物線扱いでホームがなかったために通過、
さいたま新都心駅は現在でも宇都宮線の特急が停まるホームが存在していません。
こうして見ると、特急列車が停まる駅というのは、必ずしも“今の主要駅”と一致しないことがわかります。
なぜ今の主要駅と一致しないのか?

いま、特急列車の停車駅というと「乗降者数」や「アクセス性」で選ばれている印象があります。
でも、かつて宇都宮線を走っていた特急や急行列車の停車駅をたどっていくと、
そこにはもっと長い時間をかけて刻まれた“理由”があることに気づきます。

たとえば、石橋に停車していたのは、江戸時代の石橋宿の存在が背景にあったのかもしれません。
宝積寺は、今もローカル線として親しまれる烏山線の分岐駅。
氏家も、奥州街道の宿場町である氏家宿としてにぎわった歴史があります。
そして西那須野――現在はその名で知られていますが、かつては「那須駅」と呼ばれ、 その近くには大田原宿があったといわれています。
こうして見ていくと、停車駅はただの通過点ではなく、
道の時代から続く、人の足が選び取ってきた“滞在のリズム”を引き継いでいたのかもしれません。
宇都宮から北へ伸びるこの路線は、奥州街道の延長線でもあります。
電車が停まるその場所には、実はもっとずっと昔から人が“足を止めてきた”場所が重なっていたのです。
まとめ
宇都宮線に特急列車が存在しない背景には、東北新幹線との競合や通勤路線としての性格、既存の快速・普通列車の利便性向上など、さまざまな要因が複合的に絡んでいます。特急を設定するよりも、現行ダイヤのままで通勤需要を支える方が多くの利用者にメリットが大きいため、JR東日本としても積極的に在来線特急を導入する理由は薄いのです。
一方で、ライナー列車やグリーン車など、追加料金を支払えば着席できる仕組みは整備されています。ビジネス客をはじめ「少しでも快適に移動したい」という層は、これらを活用することで特急に近い移動体験を得られます。さらに、観光需要に関しては日光方面への特急列車や東武線との競合が存在するため、宇都宮線単体で特急を設定する必要性はあまり高くないといえるでしょう。
今後も通勤需要が中心であること、新幹線の存在があること、高速バスなどの他交通機関との兼ね合いを考慮すると、宇都宮線に新たな特急列車が誕生する可能性は低いとみられます。しかし、利用者のニーズに応じて座席指定サービスやダイヤ改正による快速列車の増発など、利便性向上の取り組みが続けられることが期待されます。乗車前に最新のダイヤ情報やグリーン券、各種サービスを調べることで、より快適な鉄道旅を楽しむことができるでしょう。
あえて急がず移動することで、かつての面影も見ることができるかもしれません。